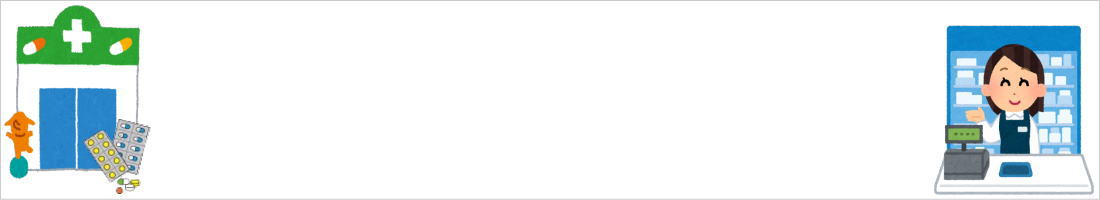薬局に勤務する調剤薬局事務は、調剤報酬請求事務を行う場合、次の紹介する医療保険の種類や取り扱い申請についてもよく理解しておくべきです。
代表的な医療保険の種類は2つ
社会保険(被用者保険)は健康保険法に基づいており、国民健康保険は国民健康保険法に基づいて制度運用されています。
社会保険(被用者保険)の種類と概要
社会保険は業務以外で発生する疾病・負傷・死亡・分娩に関して給付され、一般企業などに勤める社員・勤労者やその扶養家族が対象となる医療保険です。
社会保険(被用者保険)には次のような種類があります。
- 組合管掌健康保険:
独自に設立運営し厚生労働大臣から認可されている健康保険組合をいいます。 - 政府管掌健康保険:
健康保険組合が設立されていない中小企業などに勤める従業員・労働者が加入する健康保険をいいます。 - 共済組合:
共済組合が独自運営している健康保険をいい、公立・私立教職員・国家公務員・地方公務員などが加入しています。 - 船員保険:
船員のための保険制度になり、通勤途中・業務中・業務外すべてに適用され、病気・怪我・傷害に対して保険給付されます。この点が上記3つの各種保険との大きな違いです。
国民健康保険の種類と概要
- 国民健康保険組合:
職域保険とも呼ばれ、自営業者・農業従事者などが加入している健康保険をいいます。社会保険と国民健康保険は、何らかの職業に就いている方が加入している保険なので、職域保険と言うわけです。
- 市町村国民健康保険:
職域保険である国民健康保険組合や社会保険(被用者保険)などどこにも加入していない方が対象になる健康保険をいいます。職業ではなく、市町村に居住している地域の方を対象としているので地域保険とも呼ばれています。
老人保健制度と後期高齢者医療制度
高齢者に対して医療と保健の両面からサービス提供を行い、高齢化社会に対応する目的で設けられた制度が老人保健制度というものでした。
老後に対して適切な医療を提供し、健康を維持するために、医療給付と共に保健事業も行い、疾病の未然予防や身体の機能訓練などを担っていたため、保健という名称が使用されています。
高齢者数が急激に増加し、医療費の財政負担も増加し続けており、一つの健康保険制度からの負担額だけでは制度を維持できなくなるという懸念から、2008年に後期高齢者医療制度に移行され新たにスタートし現在に至っています。
受給者資格は、後期高齢者の75歳以上の方、前期高齢者の65歳以上75歳未満で寝たきりなど障害を抱えている方が保険の給付対象になります。
公費負担医療制度の取扱いについて
公衆衛生・社会福祉の維持・向上を目的として、国や市区町村が費用を負担する医療制度のことを公費負担医療制度といいます。
公費負担医療制度は、個々の制度の運用根拠となる法律に従い、公費から国や市区町村が負担し、制度運用されています。
薬局が公費負担医療制度に基いても発行されている全ての処方せんに対応するには、個々の医療制度に取り扱い申請を行い指定薬局として許可を得る必要があります。
公害健康被害補償制度の取り扱いについて
大気汚染などが原因で健康被害を被った方を対象とし救済する補償制度を、公害健康被害補償制度といいます。
公害健康被害補償制度における公害疾病の認定を受けた患者には、公害医療手帳が発行され医療費を自己負担する必要はありません。
公害医療の場合は、都道府県などの公害保健課窓口に直接請求を行う必要があります。
また、他の医療保険とは区別されており、保険点数の算定の仕方も少し違います。
薬局が取り扱うには保険薬局の指定を受けることで可能になります。
労働者災害補償保険の取り扱いについて
一般的には労災と呼ばれているものですが、通勤途中や就業時間中に起こった事故などによる怪我や障害、疾病や死亡が保険給付の対象になり、これ以外に福祉事業も行なっています。
薬局が調剤などの療養の給付を扱うには、保険薬局として指定を受けるだけでは応需できません。
薬局が所在している地域を管轄している都道府県労働局長に届け出を行い、労災保険薬局として指定される必要があります。
労災保険薬局として指定されていない薬局が労災患者の処方せんを取り扱うには、一旦患者に全額自己負担してもらって、かかった費用明細が記載された領収書を患者に発行した後、直接患者が請求することになります。
労働者災害補償保険も他の医療保険とは区分されており、患者が従事する会社所在地を管轄している労働基準監督署に請求手続きを行うことになります。
日本スポーツ振興センター法による医療の取り扱いについて
学校の校内や管理下で義務教育を行っている最中に児童や生徒が怪我や負傷をしたり、文部科学省令で規定されている疾病を発症した場合に給付される制度のことです。
独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づいて運用されている公的な災害共済給付制度です。
薬局が取り扱うには、保険薬局として指定を受ける必要があります。
調剤報酬請求は、医療保険と同様の手続きで行いますので、医療保険に加入している被保険者には、自己負担分の費用を請求し、残りは保険事業を運営しているスポーツ振興センターに請求することになります。