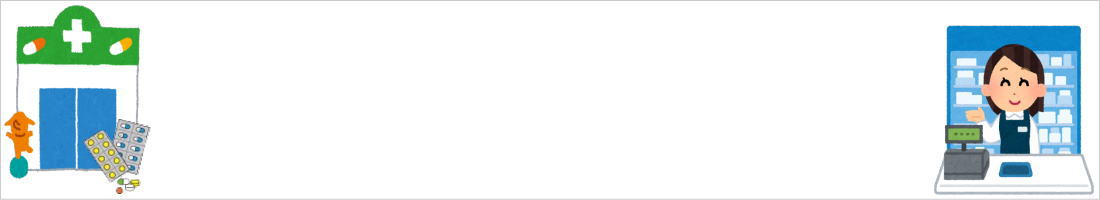医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の安全性や有効性などの規制に関しては、現在「医薬品医療機器等法(旧 薬事法)」という法律で定められ運用されています。このページでは、薬事関連の法律について、当時大きな転換期となった2005年4月の抜本的改正内容について今一度振り返り、医薬品医療機器等法(旧 薬事法)の目的や意義について考察していきます。薬局に従事し医薬品に関わる業務を担う調剤薬局事務としてもし...
医薬品に関する法律基礎知識|記事一覧
医薬品はいくつかの種類に分類され特徴も異なっていますし、個々の薬に至っては膨大な種類が存在します。ここでは、医薬品の主な種類とそれぞれの特徴があり、調剤薬局事務、登録販売者、薬剤師などが在籍する薬局での取り扱い方、法律上の規制などについて調剤薬局事務の視点で振り返っていきたいと思います。医療用医薬品の分類と特徴 医療用医薬品は、病院に診察に訪れた患者の病状を見極めた医師や歯科医師が、治療に要する...
医薬品と医薬部外品との違いは、治療目的で使用されるものなのかどうかという点です。病気や怪我を治療する目的で使用され薬の効果に有効性が認められるものを医薬品といい、症状を事前に予防・防止する目的で使用されるものを医薬部外品といいます。医薬部外品の特徴 医療機器や器具以外で、緩和な作用を人体に対して与えますが、医薬品として認可されていないものを医薬部外品と呼びます。医薬品・医療機器等に関する法律(旧...
保健機能食品制度とは何か? 最近では、健康管理に気を使う消費者も多くなり、健康食品も様々な種類が市場で販売され個人の食生活のパターンが多様化してきました。医薬品に関しては、医薬品・医療機器等に関する法律(旧薬事法)などで、次のように様々な法規制が設けられています。品質、有効性、安全性について厳格な審査製造・輸入・販売などの承認許可表示や広告の規制 一方、健康食品については、以前は食品衛生法の中で食...
医薬品を使用してもし万が一副作用などが発生し健康被害を被った場合は、被害者を救済するための公的な法的制度が設けられています。申請時には必要となる書類を全て準備し提出することで、承認されれば救済給付の支給を受けることが可能になります。但し、副作用を発生させたと考えられる医薬品の種類や健康被害を及ぼした副作用の症状の度合いによっては、救済制度が適用されずに給付が受けられないケースもあり得ます。医薬品...
生物由来製品感染等被害救済制度とは何か? 生物由来製品感染等被害救済制度の制定は2004年で、医薬品副作用被害救済制度と同じようなしくみで制度運用されています。生物由来製品とは、材料や原料として人間やそれ以外の植物を除いた生物に由来するもので製造された医療機器や医薬品のことを指します。生物由来製品に該当するものには次のような製品がよく知られていますが、その種類は多岐に渡ります。血液凝固因子などの血...
毒薬・劇薬の特徴と取扱いについて毒薬・劇薬の特徴とは 毒薬・劇薬とは、その使用によって副作用や中毒で人の身体に強い悪影響を及ぼす可能性がある薬のことを指します。動物又は人に使用することで、次のような特徴が表れる場合は、毒薬・劇薬として厚生労働大臣が指定することとなっています。副作用・薬理作用・蓄積作用が強いもの中毒量・薬用量の幅が小さいもの安全域が狭いもの毒薬・劇薬の表示と取扱い方法 容器や包装に...
下記サイトでは、通信講座や全国の通学講座の費用・受講期間・特徴・開催場所などを一覧比較し、希望する講座案内資料を最短3分で無料一括請求でき、最新の講座開講状況や内容を比較検討できます。