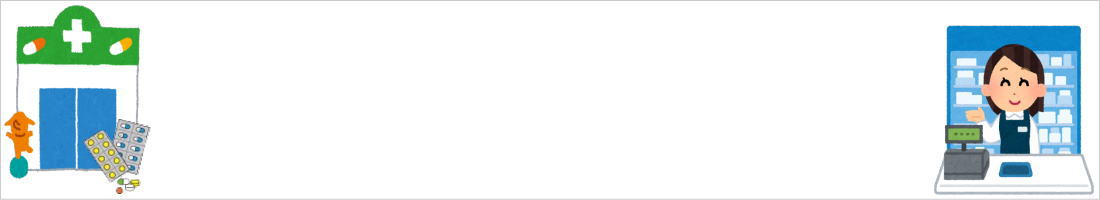生物由来製品感染等被害救済制度とは何か?
生物由来製品感染等被害救済制度の制定は2004年で、医薬品副作用被害救済制度と同じようなしくみで制度運用されています。
生物由来製品とは、材料や原料として人間やそれ以外の植物を除いた生物に由来するもので製造された医療機器や医薬品のことを指します。
生物由来製品に該当するものには次のような製品がよく知られていますが、その種類は多岐に渡ります。
- 血液凝固因子などの血液製剤
- 献血で提供される輸血用血液
- 血漿、血小板などの成分血液
- 動物由来の蛋白質が添加された医薬品やワクチン
生物由来製品感染等被害救済制度では、適正に生物由来製品を使用したにも関わらず、使用した製品などに混入していた細菌やウイルスなどにより人体に感染し、その結果、障害や疾病などの健康被害が生じて入院治療が必要となる程度の損害を被った被害者を救済することが目的になります。
また救済対象は、一時感染だけでなく、二次感染や感染後の発症予防などに対しても適用されます。
これまで発生した主な感染症では、次のような症例が有名です。
- B型肝炎、C型肝炎、エイズ:血液や血液製剤から感染・発症
- 狂牛病(牛海綿状脳症、BSE):食品から感染・発症
- クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD):食品から感染・発症
- 伝達性海綿状脳症(TSE):異常プリオン蛋白により感染・発症
これら以外にも、生物由来製剤による未知の感染症が将来発生する可能性があり、発生率を完全にゼロに抑えることは非常に難しい状況にあるのも事実です。
ですが、国や製薬会社は、未知の感染症が発生しないよう医薬品の原料や製造過程における輸入検査工程管理を厳格に徹底して実施しています。
予防接種健康被害救済制度とは何か?
1970年に予防接種健康被害救済制度が制定されてから以降も継続して改正され現在に至っています。
予防接種など他責による健康被害者を救済することが予防接種健康被害救済制度の目的になりますが、任意で予防接種を受けて健康被害を被った場合は、医薬品副作用被害救済制度が適応されます。
18歳未満対象の障害児養育年金、18歳以上対象の障害年金を受給している方の中で、在宅1級・2級に該当している方に対して介護加算が行なわれています。
救済支給を受けるには、市町村にある予防接種課か保健所にて手続き申請が可能です。
健康被害が発生した場合、医師による診断が行われますが、実施後速やかに「予防接種後副反応報告書」を作成し、市区町村の行政長へ報告することになっています。
医薬品と製造物責任法(PL法)との関係性について
製造・生産した製品に欠陥があり、それが原因で消費者が被害や損害を被った場合、製造業者の過失の有無とは別に、損害賠償責任を製造業者が負うことを定めた法律のことを製造物責任法(PL法)とい言います。
損害賠償については、製品が有する欠陥と消費者側の被害状況との関係性を証明できるれば賠償を受けることが可能です。
これに対して医薬品の場合は、元々副作用が発生する可能性を有していることが前提条件として販売されている製品なので、製造欠陥品という条件に該当しないという特性があるので、万が一副作用が発生し健康被害を受けた場合でも製造物責任法(PL法)の対象となることはありません。
これは、薬が有する治療効果の有効性と副作用による健康被害の程度を天秤にかけて比較した結果、若干の副作用があっても薬効の有効性が上回り治療効果が勝ると認められる場合は使用できる製造物だからです。
通常、副作用が発生した場合の救済措置は、医薬品被害救済制度に基づいて実施されます。
但し、医薬品は薬を適切に服用するための用量用法・注意事項などを記載した情報と薬の現物とがセットになった物が医薬品という製造物になるので、もし安全に使用するために必要となる情報や指示事項が記載されていない状態で医薬品販売した場合は、製造欠陥品にあたりPL法の対象となります。
医薬品副作用被害救済制度、生物由来製品感染等救済制度の給付種類・内容・請求期限について
| 給付の種類 | 給付・補償内容 | 請求期限 |
|
疾病について医療を受けた場合 入院を必要とする程度 |
医療費: 医療手当: |
2年以内。 |
|
一定程度の障害の場合 日常生活が著しく制限される程度以上 |
障害年金: 障害児養育年金: |
無し。 |
| 死亡した場合 |
遺族年金: 遺族一時金: 葬祭料: |
5年以内。
但し、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金が支給済の場合は、死亡後2年以内。 |