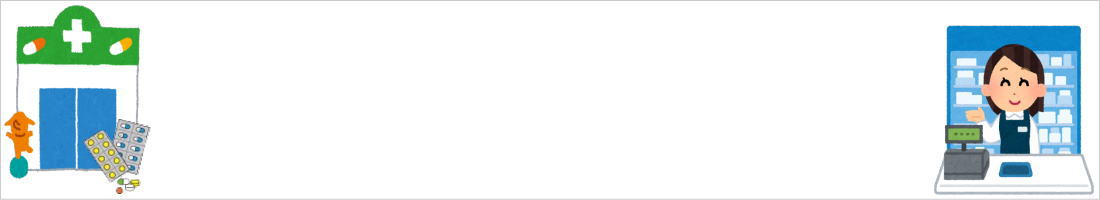調剤技術料の報酬計算は、調剤基本料(加算)+調剤料(加算)として算出されますが、このページでは調剤料について解説していきます。
調剤料とは、処方箋をもとに、保険薬局で薬剤師が医薬品を調剤する作業技術に対し算定されており、医薬品の処方日数・種類により点数は異なっています。
また、以下のような特別な作業などが発生した場合にも、その技術料として点数が加算されます。
- 薬の飲み込みが困難な患者の場合:錠剤を粉状にする。
- 複数の薬をセットで服用する患者の場合:服用時間帯ごとに薬をワンパックにセットするなど。
以上について調剤薬局事務は、調剤報酬請求することになります。
また、内服薬の調剤料に関しては、内服薬、屯服薬、外用薬、注射薬ごとに調剤科の算定を行います。
薬の1剤の定義・捉え方について
1回の処方において服用時に同一種類の内服薬を服用する場合は、薬包を個別に調剤した際も1剤として算定を行います。
服用時点において同一薬剤を服用する場合は、投与日数に関係なく1剤として算定を行います。
服用時点が同一の定義については、薬剤2種類以上に関して、服用する1日全体で服用時点で同一のことを指します。
次の項目に該当する場合は、個別に算定可能です。
- 配合不適など調剤技術上において必要な調剤を行った場合
- 内服用の液剤と固形剤(散剤・錠剤・カプセル剤等)の場合
- 服用方法(舌下錠・チュアブル錠と内服錠等)が異なる場合
薬剤の種類と調剤料の算定方法について
| 薬剤の種類 | 調剤料の算定方法 |
| 内服薬 (浸煎薬、湯薬は含まない) |
1剤ごとに算定する。(受付1回の処方せんでは3剤までだが、内服用滴剤は含まない。)所定点数は投与日数より異なり、4剤以上の時も3剤として算定すること。 |
| 頓服薬 | 激しい痛みや発作がある場合、時々の状況に応じて飲む薬のことを頓服薬という。 屯服薬は剤数により算出するのではなく、1回の処方せん受付に対して所定点数を算定する。 屯服薬に該当するかの判断基準は、処方せんの記載内容をチェックする。 用法について「〜包」、「何回分」、「〜P」などと処方せんの指示項目として記載されている場合は、屯服薬とみなす。 |
| 浸煎薬 | 保険薬局で生薬を浸煎し液剤状態にしたものを浸煎薬という。 処方日数に関係なく、1調剤ごとに所定点数を算定する。1回の処方せんでは3調剤まで、4調剤以上は3調剤で算定する。 |
| 湯薬 | 保険薬局で生薬2種類以上を混合調剤し、患者が服用する目的で煎じる量毎に分包したものを湯薬という。 投与日数により所定点数が異なり、1回の処方せんでは3調剤まで4調剤以上は3調剤で算定する。 |
| 注射薬 | 保険薬局にて調剤する注射薬は、自己注射用薬剤で在宅医療で使用される。 調剤の日数や剤数に関わらず、1回の処方せん受付ごとに所定点数を算定する。 厚生労働大臣が規定した施設基準を満たし届出している保険薬局において算定可能。 注射薬2種類以上を無菌的に混合し次に該当する場合は、1日分の製剤ごとに加算する。
|
| 外用薬 | 1回の処方で数口投与をしても、1調剤ごとに所定点数を算定する。 1回の処方せんでは3調剤まで、4調剤以上は3調剤で算定する。また、口に入れるトローチは、経口投与する薬ではないため外用薬として算定する。 |
| 内服用滴剤 | スポイトを使い服用する内服用液剤を内服用滴剤という。 内服用液剤に該当し、使用量が1滴又は数滴など1回分が極少量のもので、スポイトで分けて使用するものを内服用滴剤という。使用する液剤の量ではなく、滴剤の種類ごとに算出する。 |