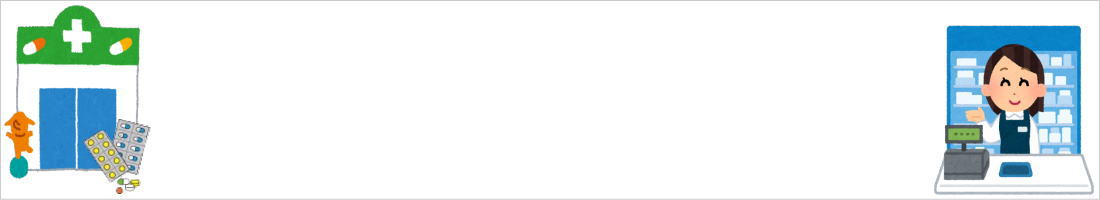調剤薬局で必要な医薬品知識とは何?
調剤薬局事務として業務を行う際には、医師が発行する処方せん通りに調剤報酬の算定を行う必要があるため薬剤の分類(注射・内服・屯服・外用)に関しては必ず理解しておく必要があります。
薬の専門知識となる薬剤の効果・効能、相互作用に関しては、調剤業務を行う薬剤師が担っているので、理解しておいて損はありませんが、詳細まで知る必要はありません。
調剤薬局事務からスキルアップするための手段は何があるの?
まず第一には、医療事務の資格を目指す方法があります。
医療事務と調剤事務は習得すべき学習範囲で重なる部分がありますが、医療事務の方が学ぶ範囲が広くなりますので、さらに知識を高めることが可能になります。
第二には、調剤薬局事務から将来スキルアップを目指し登録販売者として働くためには、薬剤や薬事法に関しても専門知識などを理解する必要があります。
調剤薬局事務の職員として勤務している方なら登録販売者の資格取得を目指すのは間違いなくスキルアップに直結します。
収入面に関しても資格手当がある調剤薬局も多くあるので、月給もアップすることが期待できます。
調剤薬局事務の勉強方法は?
調剤薬局事務の資格講座は次のように多くの団体が主催して講座を開講していますので、自分のライフスタイルを考慮して資格講座を選択してみましょう。
- 社会人を対象とした調剤報酬請求事務の知識を習得する短期講座
- ハローワークで雇用保険を財源に行われている求職者支援制度での無料の調剤事務講座
- 調剤報酬請求事務を履修科目として組み込んでいる専門学校や短期大学
ハローワークの求職者支援講座では、下記のような科目について約325時間程度の教育が行われています。
- 病院概論
- 医療保険制度
- 薬剤知識
- 医学知識
- 患者接遇
- 診療報酬請求事務
- 調剤報酬請求事務
- 報酬明細書(レセプト)作成演習
- 医事コンピュータ入力操作スキル
上記の学習時間はトータルで約190時間程度になるので、残りの135時間はパソコンスキルの習得に当てられます。
調剤薬局事務の資格取得後の就職先、勤務形態は?
近年の薬局業界では出店、統廃合が頻発しており、雇用形態も多様化した中で人材採用が行われていますし、ありきたりですが正職員・パート職員・アルバイトでの求人が主流ですが、医療業界専門の派遣会社もあり派遣の雇用形態で採用している薬局も少なくありません。
調剤薬局事務の業務上のクレームは多いの?
日々、様々な病を患っている方が調剤薬局には来局されるので、当然クレームは起こり得ると覚悟しておく必要があります。
クレームの中でも、待ち時間が長い、薬の渡し間違いは多いようです。
待ち時間が長い状態が頻発すると集客に大きな悪影響が発生するので、調剤薬局では対応策を考えている所が多くあります。
また、薬の渡し間違いは、大きなトラブルに発展することがあるので、薬剤師が調剤を行った後も調剤事務職員も含めてダブルチェックを実施するなど、絶対に間違いを起こさないようなチェック体制を講じることは重要です。
患者さんの中には、薬局でのトラブルや薬のクレームを保健所などに通報し苦情を訴える方もいるので、原因を明確にして対策を講じておかないと調剤薬局の経営に損害が発生することになるため小さなクレームでもスルーせず適宜、適切に対策することが重要です。