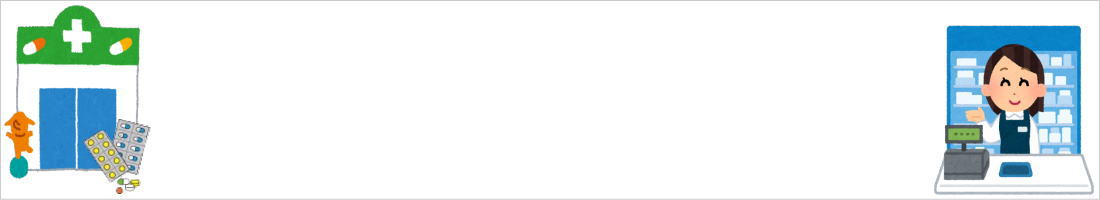調剤薬局は全国に数多くありますが、この職場ではどのような専門的知識やスキルを身に付けた専門家や資格保持者が業務に従事しているのかを見ていきたいと思います。
調剤や医薬品販売の仕事をするのに何か資格は必要か?
調剤薬局に従事し、医療用医薬品、すなわち医師が発行する処方せんに基づき調剤業務を実施するためには、薬の専門家である薬剤師の資格を必ず取得していなければなりません。
無資格で調剤業務を行ない患者さんに薬を処方したりすることは法的に禁じられています。
また、現在は政府が医薬分業を施策として積極的に推進してきた影響もあり、一般用医薬品、別の呼び方はOTC薬と呼ばれる薬の販売を行う薬局やドラッグストアなどが全国に数多く出店し増加し続けてきました。
一般用医薬品(OTC薬)に分類される薬剤の中には、薬剤師免許を持っていなくても患者さんなどに販売することが許可されている薬もあります。
ただし、誰でも自由に販売できるのではなく登録販売者試験に合格し資格取得する必要があります。
厳密にいうと、登録販売者とは、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品に区分されている一般用医薬品のうち、第2類医薬品、第3類医薬品に限り販売することが認められている専門資格です。
登録販売者の資格は、年々患者が増加し続けている現状に対応するため、専門性を高め安全面を確保するために推進されてきた医薬分業によって新しく誕生した資格とも言えます。
薬剤師免許を持っていれば、第1類から第3類まで全ての医薬品を扱うことが可能なため、従来から薬剤師が全ての薬に対応していました。
しかし、第2類・第3類医薬品の販売を登録販売者に任すことで、薬剤師が調剤業務、服薬指導、患者からの相談業務などに、特化して時間を割けるため本来業務に集中することが可能となり、患者の満足度と安全性をさらに高めることに繋げることが出来ます。
資格取得する場合、薬剤師は国家試験になり、大学で薬学について専門的に学ぶ必要がありますが、登録販売者の資格は誰でも受験でき、学歴も関係なく試験に合格すれば資格を得ることが可能です。
薬事法改正により、一般販売業の店舗でも一般用医薬品の取り扱いが許可されているので、登録販売者が活躍できる場は広範囲にわたっています。
調剤請求事務の仕事をするのに何か資格は必要か?
調剤薬局には、調剤報酬明細書(レセプト)を作成し調剤報酬を請求するという重要な業務があり、このような仕事を担っているのが、調剤事務員となります。
調剤事務員の多くは、当サイトでも紹介している調剤薬局事務の資格取得者ですが、調剤報酬請求事務は、無資格でも行う事は可能です。
但し、レセプト作成や点検には専門知識や技能が必要なため、調剤事務員は保険制度や調剤報酬に精通していることが求められ、一般的には調剤薬局事務の資格講座を受講し資格を取得してから就職活動に臨む方がほとんどです。
病院や診療所に勤務し受付や会計窓口で患者対応している医療事務員も調剤事務員と同じですが、国家資格ではないので、先ほど説明したように無資格でも採用されればレセプト業務であっても仕事に従事することは可能です。
しかし、現実的に仕事をスムーズに処理するには、医療保険制度、調剤報酬制度、医薬品関連法規などについての専門知識は必要となるので、まず、スクールや講座などでしっかりと学びスキル習得後に仕事に就くことが望ましいと思います。
また、調剤薬局に来局される患者さんは、それぞれ心身の状況や状態が異なりますので、患者さんとも円滑にコミュニケーションを図りながら対応するのも大切な業務の一環です。
このような意味から人を扱うという点では接客業ともいえるので、社交的で明るい性格であるほうが適しているかもしれません。
更に現在の調剤薬局では調剤報酬の算定や明細書作成などのレセプト業務はコンピュータを使用しており、他の事務作業についても、ほとんどがパソコンを使用することになるため、最低限のパソコン操作の知識や技能は必須となっています。