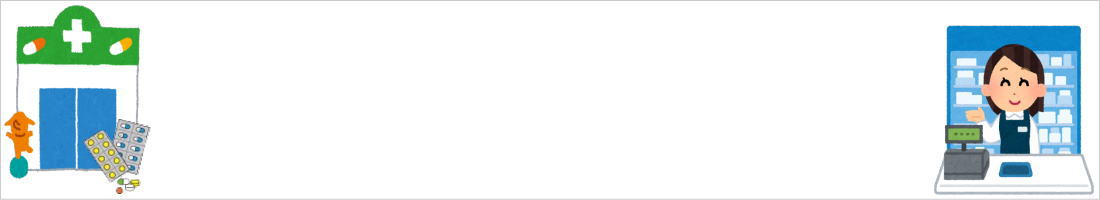1.調剤薬局の特徴・職場環境|調剤薬局事務の職場
調剤薬局事務の勤務先として一番多いのが調剤薬局になりますが、これは、現在の医薬分業の流れからして当然の結果でもあります。
医薬分業については、「医薬分業とは」のページで解説していますのでそちらをご覧下さい。
皆さんが働くことになる薬局については、薬事法 第1章 総則 第2条11項により以下のように定義されています。
「この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)をいう。」
また薬局には、基準薬局と呼ばれるものもあります。
基準薬局とは、日本薬剤師会が定める基準をクリアし認定され、特に薬剤師会が推奨する薬局をいい、通常、「かかりつけ薬局」と呼ばれます。
調剤薬局(保険薬局)とは、わかりやすくいうと、病院や診療所からは独立した薬局で、 医師が診断した後に処方箋を発行し、それに基づき調剤した処方薬を、患者さんに処方することのできる薬局をいいます。
現在、調剤薬局は厚生労働省の医薬分業の推進に伴い増加傾向にあります。
病院や診療所などの医療機関から院外の調剤薬局に出された処方箋の枚数をみてみると、平成19年度は平成9年度の2.02倍にもなっており大幅に増加しています。
当然調剤薬局数も増加していますので、調剤薬局事務のお仕事をする チャンスは大きく広がってきると考えられます。
2.ドラッグストアの特徴・職場環境|調剤薬局事務の職場
調剤薬局事務の勤務先としては、ドラッグストアにもニーズがあります。
ドラッグストアとはなにかというと、日本チェーンドラッグストア協会では、「医薬品と化粧品、そして、日曜家庭用品、文房具、フィルム、食品等の日用雑貨を取扱うお店」と定義されています。
ドラッグストアでは、一般医薬品を取り扱うために、営業時間中は、必ず薬剤師を1名、お店に在籍させることが義務付けられています。
また、医薬分業の流れや2009年6月の薬事法改正に伴い、院外処方箋を発行する病院や診療所が増加してきたことにより、ドラッグストア店内に調剤室を設けて調剤併設とし、処方箋に基づき薬の処方も行うようになるドラッグストアも増えてきました。
日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)が発表した「2008年度日本のドラッグストア実態調査」によると、全国のドラッグストア総店舗数は15,625店舗で、前年よりも241店舗増加しているとのことです。
2000年度よりデータが収集されており、日本のドラッグストア業態の動向と変化を明らかにすることが目的です。
また2000年度の調査以降、店舗数と総売上高は、毎年のように増加しており、健康ブームともあいまって、ドラッグストアが国民生活に深く浸透し拡大していることがわかります。
現在では日本各地で多くのドラッグストアの店舗が開店しています。
この流れは今後も進んでいくと考えられますので、本格的にドラッグストアが調剤薬局の業務を行うとなると、調剤薬局事務の必要性も全体的に高まります。
そうすると、調剤薬局事務の人材を採用する会社も多くなり、調剤薬局事務のお仕事を目指している人にとっては、就職する機会がますます飛躍的にアップすることも考えられます。
このような現状から、今後は調剤薬局事務の人材へのニーズがますます高まってくるのではないかと見られています。
3.病院の特徴・職場環境|調剤薬局事務の職場
調剤薬局事務の勤務先としては、調剤薬局やドラッグストア以外に、病院があります。
病院以外の医療機関(診療所や医療モール)は、薬剤師の配置基準がないため、薬剤師が不在の場合も多く、ほとんどが院外処方ですが、大きな病院は、病院内に薬局を設置しているところもあります。
このような病院では、医師が診察後、処方箋をだし調剤薬局と同じように処方箋を院内薬局に持っていくことにより薬を処方してもらうことになります。
また現在の医療機関では、作業を細分化して効率よく対応するような傾向も強くなってきているようです。
このことから、薬に関しても業務をいろりろ分担し、仕事を行うところも比較的多くあるようです。
院内での医薬分業とも呼べるかもしれません。
以上のように調剤薬局事務のお仕事は、いくつかの職場で活躍することができます。