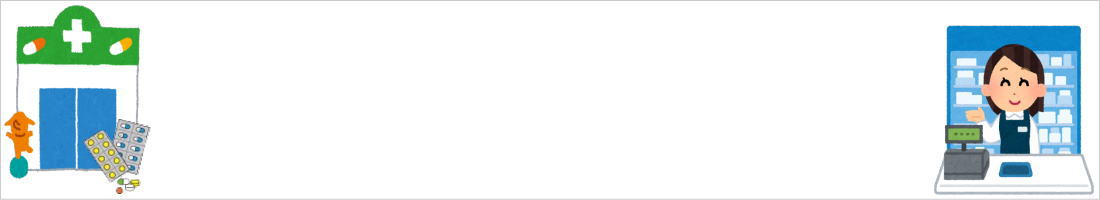医療保険制度の改革の流れ
健康保険法が1927年に日本では施行されスタートしましたが、その後、国民健康保険法が戦後に制定されました。
現在の日本の医療保険制度では、日本国民であれば、なんらかの医療保険に加入することが義務付けられている国民皆保険という仕組みが取られています。
病気になったり、怪我をした時でも国民皆保険制度のおかげで、少ない負担で誰もが質の良い公平な医療サービスの提供を受けることができるようになりました。
それ以降現在に至るまでには、経済状況の浮き沈みや少子高齢化が世界に類を見ないほど急激に進展し、医療保険財政の負担が増大し圧迫されています。
そのような過程で政府は、医療保険制度の改革を1980年過ぎから頻繁に実施しており、各制度の給付割合を変えたりして、なんとか制度を維持してきました。
老人保健制度は2008に後期高齢者医療制度に移行されるという大きな制度改革が実施されました。
これらの制度改革は保険調剤を行なう薬局や調剤報酬請求事務を一手に担う調剤薬局事務スタッフの業務に直接関係することなので、影響や状況をしっかりと見据え、制度全般に対する知識の理解が不可欠です。
医療保険制度の理念とは
医療保険、後期高齢者医療制度(旧 老人保健制度)、公費負担医療の3つが医療保険制度の大きな柱になります。
医療保険制度とは、相互扶助の考え方にもとづき、働く人々やその家族が病気・ケガ・死亡・出産などがあった時に、安定した生活ができるように、医療給付や手当金などを支給する社会保険制度です。
医療保険加入者が、予期せぬ病気やケガに備え、年収に応じた保険料を出し合って、診療を受けたときに、保険から医療機関(病院・診療所・保険薬局など)に、医療費を支払うしくみです。
日本国憲法の第25条でも、 次のように規定されています。
- すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する(健康権の保障)
- 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない(社会福祉・社会保障・公衆衛生の保障)
日本では社会保険により医療を保障しており、現在の医療保険制度は、働いている職域によって加入できる保険制度が、大きく分類すると次のように異なっています。
- 国民健康保険・・・自営業や農業を営んでいる人が加入する保険
- 健康保険会社・・・工場・商店等で働いている人が加入する保険
医療保険制度の特徴
日本の医療保険の大きな特徴としては、以下の3点です。
- 国民皆保険制度:
全ての国民(日本在住の外国人も含む) は、医療保険に加入する権利および義務を有する。自分の意志で医療保険に加入しないという選択はできません。
- 現物給付と出来高払い:
医療機関(病院・診療所など)を受診した患者は、医療サービスという現物で給付を受け取ります。また医療機関は、患者に施した医療サービスに応じて国で定められている診療報酬を受け取ります。
- 割安な医療費と受診が容易:
日本の医療機関はかなり整備されており、患者が負担する診療費の自己負担金額が、医療費の3割ほどに抑えられていることにより安心して誰もがすぐに医療サービスを受けることができます。