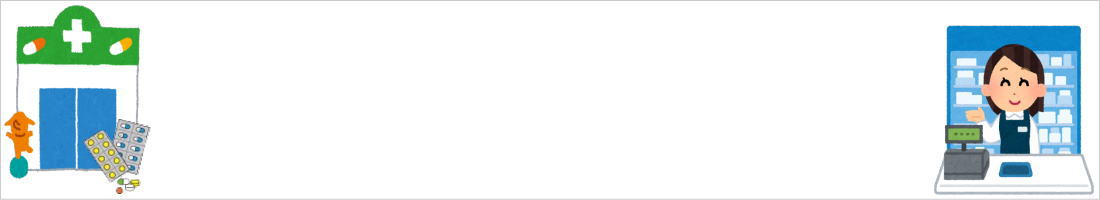医療保険制度に定めに基づき、薬局での調剤薬局事務の主要業務である保険調剤報酬の算定や、保険薬局での保険調剤などの業務が実施されています。
また、申し出がない限り保険薬局では、居宅療養管理指導者として厚生労働省令に基づいて指定を受けることが可能で、薬剤師などが医師の指示事項に従い、在宅介護業務として薬学的な管理及び指導を行なうことが許されています。
保険調剤業務が行える薬局は保険薬局と呼ばれており、その保険薬局で働いている薬剤師は保険薬剤師と呼ばれています。
保険薬局を開設するためには都道府県知事の許可を受けることが必要になり、保険薬剤師になるには免許が必要になります。
ここでは、保険薬局と保険薬剤師とは何か、保険制度上どのように規定されているのかについて詳しく見ていくことにしましょう。
保険制度における保険薬局の規定内容
保険調剤業務は健康保険法上の療養給付の一つになりますが、この業務を行う許可を得た薬局のことを保険薬局と呼びます。
医療保険制度では、医療用医薬品の調剤を行う場合、保険医が発行した処方せんが必要になり、薬剤師がこの内容に従って実施する調剤を保険調剤と呼びます。
保険薬局として営業するには、まず医薬品医療機器等に関する法律(旧薬事法)の定めに従い、都道府県知事薬局から許可を受け、さらに薬局の店舗所在地を管轄する地方社会保険事務局長を通じて、厚生労働大臣から指定を受けて調剤業務などを行うことができます。
要するに、薬局の営業許可を受けているだけでは、健康保険法で規定されている保険調剤の業務は行うことはできないということです。
保険薬局として指定を受けていない薬局では、保険外調剤しか行うことができません。
また、保険薬局の指定を受けているからといって、保険調剤に関するすべての行為が許可されているというわけではありません。
通常、被用者保険である社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度などに基づくものに関しての保険調剤は保険薬局の指定を受けることによって原則行うことが可能です。
日本の医療保障制度には、医療保険と後期高齢者医療制度が主な制度になりますが、この他にも、2000年に施行された介護保険制度、公費負担医療制度、労働者災害補償保険、公害健康被害補償制度などに基いた様々な保険制度があります。
なので、保険薬局の指定を受けると共に、各種制度の運用基準となる法律に基いた指定も受ける必要があります。
例えば、医師が発行した処方せんに麻薬が記載されている時は、麻薬小売業者の免許取得が必要で無い場合は無断で取り扱うことは違法になります。
また、病院に通院することが難しい患者さんに対して薬剤師が行う在宅患者訪問薬剤管理指導も、無届出では実施することはできません。
医療機関から発行される処方せんすべてに対応し、保険薬局として医薬品の調剤業務を行えるようにするには、全ての各種保険制度に基づいて指定を受け、取り扱い許可を得ることが必要です。
保険薬局の指定についてまとめると、都道府県知事から薬局の営業許可を得て、厚生労働大臣からの指定を受ければ、保険薬局として保険調剤業務を行うことができ、社会保険(政府管掌健康保険、組合管掌健康保険)、国民健康保険(国民健康保険組合、市町村国民健康保険)、後期高齢者医療制度(旧 老人保健制度)について扱うことができます。
その他の保険制度については、その各種制度の運用根拠となる法律に従って指定を受けることで、公費負担医療制度、労働災害保償保険などについての保険調剤業務を担うことができます。
保険薬剤師の登録手続きについて
保険調剤は、薬剤師免許を取得しているだけでは行うことはできません。
薬剤師が勤務している保険薬局の店舗所在地を管轄している地方社会保険事務局長に届け出を行い、保険薬剤師として登録されることが必要です。
但し、保険調剤を行えるのは、保険薬剤師として登録した保険薬局のみに限られています。
掛け持ちでいくつかの薬局で保険調剤を行う場合は、薬局毎に保険薬剤師として登録する必要があります。
また、現在勤めている薬局から他の都道府県に所在地がある薬局へ勤務変更となった場合は、変更届けの提出が義務付けられています。
登録には更新手続きがなく、問題を起こして行政処分を受けたり、自分から登録辞退しない限りは登録が途中で取り消されることはありません。
なお、管理薬剤師の場合は保険薬剤師とは異なり、管理業務を行うために勤務している薬局でのみ登録可能となっています。
以上、保険薬剤師の登録手続きについてまとめると、薬剤師免許を保有し、調剤業務を行っている保険薬局の所在地を管轄する地方社会保険事務所局長に届け出を行い登録してもらう必要があります。
もし、勤務地が他の都道府県に変更となった場合は、変更届けが必要になりますが、更新手続きは不要です。