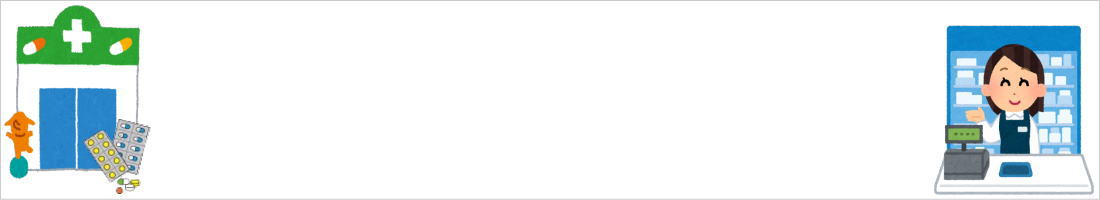医薬品を使用してもし万が一副作用などが発生し健康被害を被った場合は、被害者を救済するための公的な法的制度が設けられています。
申請時には必要となる書類を全て準備し提出することで、承認されれば救済給付の支給を受けることが可能になります。
但し、副作用を発生させたと考えられる医薬品の種類や健康被害を及ぼした副作用の症状の度合いによっては、救済制度が適用されずに給付が受けられないケースもあり得ます。
医薬品副作用被害救済制度の適応対象と給付種類
本来、医薬品は薬に含まれている薬効成分により、病気などで苦しんでいる患者の症状を緩和させたり、治癒させることを目的として使用されるものです。
しかし、医薬品が有している薬効が100%必ず有効的に発揮されるとは言い切れず、使用開始当初に全く予期していなかったような健康被害を発生させる場合があります。
医薬品の使用目的を守り、用量用法を遵守して正しく使用しているのに、重篤な健康被害を被ってしまったという事も過去に実例があり、決して他人事ではありません。
こうした想定外の健康被害にみまわれた場合、製薬会社を相手取って法的手段である民事訴訟などで裁判を起こし勝訴して賠償してもらうまでには相当長い期間が必要になってきます。
そこで、健康被害に合った患者さんを早急に経済的な面から救済することを目的として、医薬品副作用被害の救済制度が法的な賠償責任とは別途で設けられているわけです。
医薬品副作用被害救済制度の適応対象は?
適正に次のような医薬品を使用したにも関わらず、副作用の発生によって心身に障害や疾病などの健康被害が発生し、治療のために医療機関への入院が必要となった状況にある患者さんについては、医薬品副作用被害救済制度の適応対象となります。
- 病院、診療所で投薬された医療用医薬品
- 薬局などで購入した一般用医薬品(市販薬)
要するに適正な治療目的で、正しく使用していた場合に健康被害を生じ入院治療が必要となる程度の薬害を被った患者さんが医薬品副作用被害救済制度による給付対象者となります。
但し、給付対象外となる事項もあり、例えば免疫抑制剤や抗がん剤などがこれに該当します。
また、1979年に医薬品副作用被害救済制度が制定され、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(総合機構)が現在の運営団体として業務を担っています。
全ての製薬会社(医薬品製造販売業者)が納めている拠出金によって、医薬品副作用の被害者救済事業が運営され、救済を必要する患者に給付する費用が賄われています。
医薬品副作用被害救済制度の給付種類は?
医薬品副作用被害救済制度で給付される種類には、主に次の3種類があります。
- 疾病に対する給付:副作用による疾病の治療費の自己負担分など
- 障害に対する給付:日常生活が副作用により著しく制限される障害に対する補償など
- 死亡に対する給付:副作用が原因で死亡した遺族への見舞いなど
これらの給付は請求期限が各々決まっているので、注意が必要です。
また、救済給付を請求する場合は、総合機構から申請書を取り寄せて必要事項を記入し、次の必要種類と共に提出し請求手続きを行います。
- 医師の診断書及び投薬証明書:
医薬品の副作用による症状であることを証明するための書類 - 受診証明書:
副作用の治療に要した費用証明の書類
医薬品副作用被害救済制度の対象外となる事項
次の事項に関しては、医薬品副作用被害救済制度に適応せず給付対象外になります。
- 予防接種を任意に受けて被害を生じた場合は対象となりますが、法定予防接種を受けたことにより被害を受けた場合は予防接種健康被害救済制度で対応するので給付対象外になります。
- 医薬品製造販売業者側に明確な損害賠償責任が認められる場合は給付対象外になります。
- 健康被害発生の可能性があらかじめ認識されていても、救命行為のためにやむを得ず規定量以上に医薬品を使用せざるを得なかった場合は給付対象外になります。
- 給付請求期限が経過したり、健康被害の程度も軽度である場合には給付対象外になります。
- 不適正に医薬品を使用していた場合は給付対象外になります。
- 医薬品による健康被害でも厚生労働省が指定した薬剤(免疫抑制剤、抗がん剤、インターフェロン、一部の不整脈薬や抗ウイルス薬、医薬品製造専用医薬品、消毒薬、殺鼠剤や殺虫剤など)