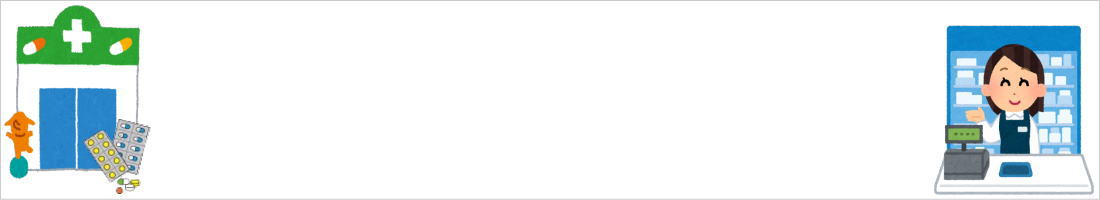医療保障制度の体系
日本の医療保障制度の体系は、主に3つの医療保険制度に分類されます。
医療保険制度
国民皆保険制度に基づき、国民全員を対象とした制度。
後期高齢者医療制度
主に75歳以上を対象とした制度。
公費負担医療制度
国や地方自治体からの公費により医療費を負担する制度。
その他の制度には、医療補償制度あり、労災保険や自賠責保険などが該当します。
医療保険制度
「国民皆保険制度」では、日本に在籍する国民は何らかの医療保険に加入する義務があり、医療保険は、次の2つに分類できます。
職域による社会保険⇒被用者保険
社会保険は、サラリーマンや公務員が被保険者として加入し、勤務先が加入する健康保険組合や共済組合などの医療保険団体が保険者として運営を行っています。
居住地(市町村)を基にした保険⇒国民健康保険
国民健康保険は、主に自営業者(個人事業主)やその家族が被保険者として加入し、市町村や一部の組合が保険者として運営を行っています。
私たちは加入している保険者に保険料を支払い、私たちが病院などの医療機関で診療行為を受けた場合は、医療に要した金額の何割かを一部負担金として医療機関の会計で支払いますが、
それ以外の金額は私たちが加入している保険者に対して医療機関が診療報酬の請求申請を行い、審査支払基金を通じて医療機関に支払われます。
病院などの医療機関が医療費の請求を行う時に作成提出する書類を診療報酬明細書(レセプト)と呼びます。
後期高齢者医療制度
2008年(H20年)4月以前は老人保健でしたが、同年4月以降は75歳以上の後期高齢者と65歳以上の前期高齢者の一部からなる後期高齢者医療制度が施行されました。
老人保健では各市町村別に保険料が決定されていましたが、
後期高齢者医療では、都道府県別で広域連合が保険料を決定するしくみになり、他の制度から独立した医療制度となっています。後期高齢者医療の保険料は原則として年金から差し引かれます。
公費負担医療制度
経済的に困窮している家庭状況にある人や、心身に障害を抱えている人、特定の病気を患っている人などを対象に、公費から医療費を負担する制度です。
公費負担医療は何種類も存在しますが、公費の種類により、一部負担金の割合や取り扱い医療機関は異なります。