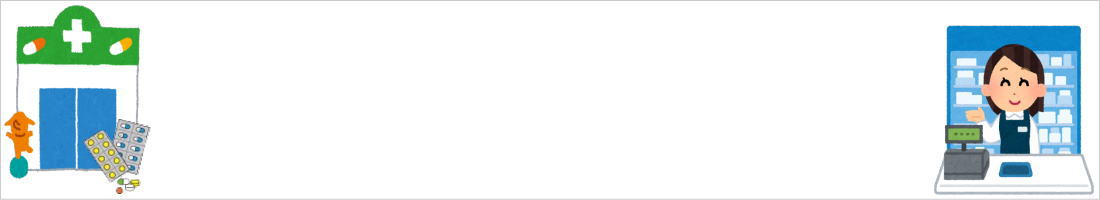患者さん本位の医療に変化!
最近ではIPS細胞に始まり、臓器移植、代理出産、医療事故など日々医療に関する新たな問題が発生しニュースなどで報道されています。
医療問題などに関心をもつ方も多くなっていることも関係していますが、医療のあるべき姿について見直しが進んでいます。
以前は医師や病院側に主導権がある形で医療が行われることが一般的でしたが、その結果、一歩通行的な医師の診療方針や外来診療での長い待ち時間など、患者側からすると快適とはいえない様々な問題が発生していました。
これらの反省を踏まえ、最近では患者のことを第一に考えた医療に病院側も大きく転換しつつあります。
そこで次に患者本位とも言える医療行為にはどのようなものがあるのか代表的なものについて解説します。
インフォームドコンセント(informed-consent)
インフォームドコンセントとは、「説明と同意」という意味です。
医師は、患者が患っている病気の症状やそれに対する治療方法について説明をする義務があり、患者もそれらについて知る権利があるという考え方のことです。
医師は難病や専門的な治療法でも、患者の理解・納得を得られるよう、それらの内容についてにきちんと説明しなければなりません。
患者側も、医師に治療をまかせっきりにするのではなく、自身が患っている病気に関しても知識と認識を持つ必要があります。
お互いにこのような意識を持つことによって、医師と患者は理解し合え、納得がいく治療を行うことが可能になります。
このような考え方からインフォームドコンセントは、患者本位の医療を行うには必要不可欠であるとされています。
セカンドオピニオン(second-opinion)
セカンドオピニオンとは「第二の診断」という意味です。
主治医(担当医師)以外の別の医師に診断を行ってもらうことをいいます。
このメリットとしては、主治医が行おうとしている治療方法が最善なのか、他にも適切な治療法があるかということの確認ができます。
セカンドオピニオンと主治医の診断結果が同じなら、安心して主治医の治療を継続できますし、異なった診断であれば、さらに適切な治療を模索することができます。
電子カルテ
電子カルテとは、医師が治療経過について記録したカルテを、コンピュータで作成・管理したものをいいます。
電子カルテは、保管棚や保管場所が不要で、パソコン一つでどこでもいつでも内容を確認できるので、急速に医療現場での導入が進んでいます。
またネットワークで繋がっていれば複数の病院や医師がカルテをすぐ確認できるので、患者が病院を変わる時でもセカンドオピニオンを受ける場合でも大変便利です。
医薬分業
以前、病院で診察を受けた場合、病院内薬局で処方した薬を受け取っている場合がほとんどでしたが、医薬分業が推進された結果、病院で処方箋を受け取り、院外の「かかりつけ薬局」に処方箋を提示して処方薬を受け取る仕組みに大きく転換されました。
その理由は、患者が受診している医療機関が複数あった場合は、「かかりつけ薬局」に何枚も処方箋を持ち込むことになりますが、薬局側では同じような薬が重複していないかなどの安全チェックが容易になります。
このことにより患者さんが安心して薬を服用できるので大きなメリットとなっています。
ジェネリック(後発)医薬品
ジェネリック医薬品とは、新薬の特許期限が切れた後、他の製薬会社で製造販売される安い価格の類似薬をいいます。
ジェネリック(後発)医薬品の使用促進は、医療制度改革の目標にもなっており大きなメリットがあります。
・特許切れの医薬品を、特許権者でない製薬会社が製造販売できれば、通常、新薬の開発には多額の投資が不可欠ですが、開発費が不要なので生産コストを安く抑えることができ薬の値段も安くなります。
・新薬として既に有効性や安全性か確認されているので新薬とまったく同じ効用が期待できます。
・薬の値段が安いので患者も医療費が安くなり、国も高騰する医療費削減につながります。